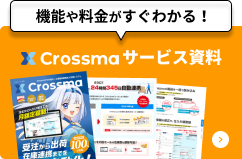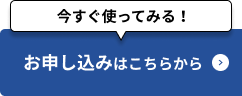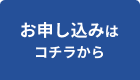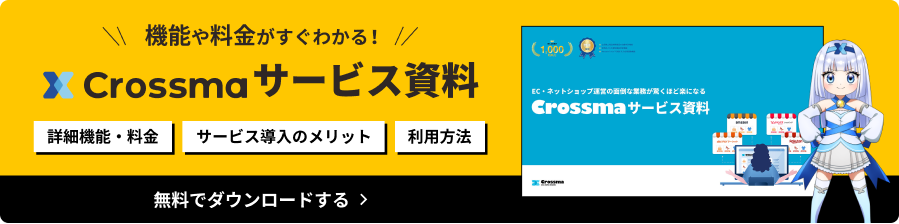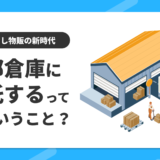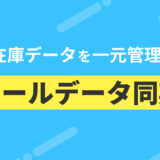今回は、とあるネットショップ店舗を例に、受注管理システムを選ぶポイントを紹介します。
目次
「エクセルでなんとか回していたけれど…」
加賀井さんのお店は、アパレルを中心に楽天とYahoo!ショッピングで販売している中堅EC事業者です。
スタート当初はエクセルを使って注文管理を行い、注文が1日数件の頃は顧客情報を手入力。
入金確認を目視で行っても大きな問題はありませんでした。
しかし、取り扱い商品が増え、セールやキャンペーンで注文が一気に増えると、エクセル管理では限界が見えてきました。
-
入力の手間で発送が遅れる
-
在庫数の更新が追いつかず、売り越しが発生
-
担当者によって管理の仕方がバラバラ
結果として、顧客から「発送が遅い」「注文したのに在庫切れ」といったクレームが入るようになり、社内も疲弊していったのです。
システム導入で変わった日常
そこで加賀井さんが導入したのが、受注管理システムでした。
システムを導入すると、
- まず注文情報が各モールから自動で取り込まれてきました。
- 入金確認や在庫数の更新もリアルタイムで反映され、各モールに見に行く必要がありませんでした。
- 出荷実績の反映もボタン一つで完結。
担当者の作業時間は大幅に削減され、残業が常態化していた現場が落ち着きを取り戻しました。
さらに、発送のスピードが上がったことで顧客からのレビュー評価も改善し、結果的にリピート購入につながる好循環が生まれたのです。
受注管理システムを選ぶときのチェックポイント
加賀井さんのように「エクセルからの卒業」を考えるEC事業者は少なくありません。
導入の際には、次のような点を確認しておくとスムーズです。
-
対応モール・カート:自社の展開先モールに対応しているか
-
在庫連携の有無:複数モールで在庫数を一元化できるか
-
操作性:現場のスタッフが直感的に扱えるか
-
コスト:月額費用と削減できる工数を比較できるか
「システムに合わせる」のではなく、「自社の運営スタイルに合うものを選ぶ」ことが成功の鍵になります。
受注管理の自動化は「選択肢」から「前提」へ
EC事業者にとって、受注処理の効率化は長年の課題です。
「エクセルでなんとか回している」段階から、「受注管理システムを導入して効率化する」段階へ、多くの事業者がすでに移行し始めています。
しかし、ここで重要なのは、受注管理の自動化はもはや“便利な選択肢”ではなく“前提条件”になりつつあるという点です。
なぜ「自動化」が必須になるのか?
理由は大きく3つあります。
-
EC市場の拡大と競争激化
ネット通販の市場は年々拡大し、出店者も増加しています。
差別化が難しくなる中で「受注・発送のスピードと正確さ」は顧客満足度を左右する要因になっています。 -
人手不足と人件費の高騰
「人を増やして処理する」時代は終わりました。
人件費は上昇し、採用難も続く中で、システムによる自動化は避けられません。 -
顧客の期待値の上昇
Amazonのように「注文した翌日には届く」スピードが当たり前になり、少しでも対応が遅いと不満につながります。
受注管理の自動化は、顧客の期待に応えるための基盤です。
未来を見据えたEC事業者の動き
例えば、アパレルを扱う加賀井さんは、エクセルでの管理からシステムに切り替えたことで発送リードタイムが2日短縮。
結果として顧客レビューが改善し、リピート購入率も上がりました。
雑貨を扱う事業者さんは、在庫連携を自動化することで「売り越しゼロ」を実現。
賞味期限管理をする時間も生まれて、フードロスの削減にも成功しました。
こうした成功事例は「効率化」の枠を超え、顧客体験の向上と売上の成長に直結しています。
今動くか、後回しにするか
受注管理をシステム化するのは「そのうちやればいいこと」ではありません。
むしろ、競争が激化するこれからのEC市場で成長するためには、今すぐ取り組むべき基盤づくりです。
早く動いた企業ほど、工数削減だけでなく「顧客に選ばれる力」を強めています。
逆に後回しにすれば、競合との差は広がる一方です。
まとめ
受注処理だけではなく、業務の自動化は、単なる業務効率化ではなく、これからのEC事業を伸ばすための必須条件。
「選択肢」ではなく「前提」として、自社の仕組みを見直すタイミングに来ているのではないでしょうか。
クロスマでは、こうしたECの未来を見据えた情報を今後も発信していきます。
クロスマなら、出品後は全て自動化できます。具体的に知りたい方は、ぜひクロスマまでご相談ください!