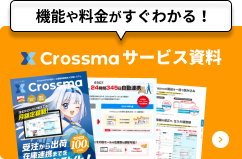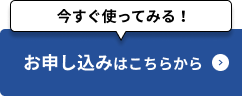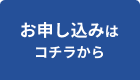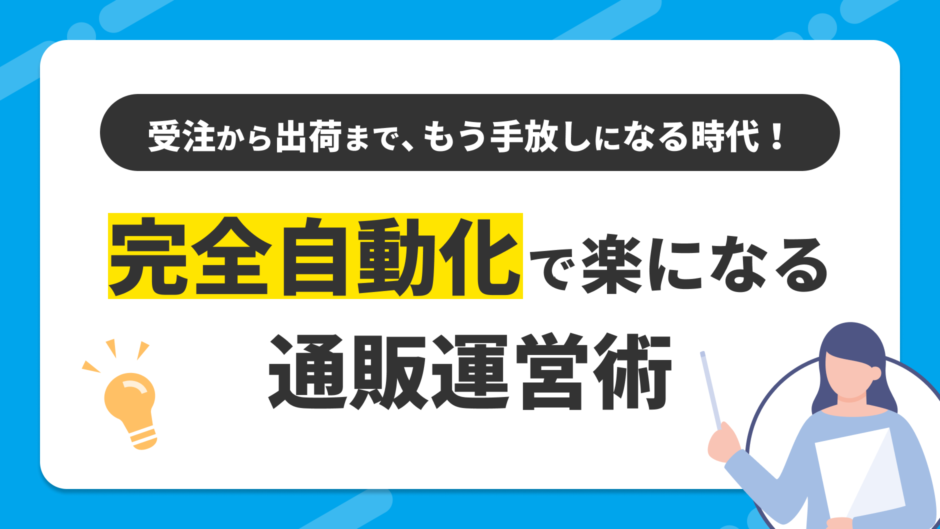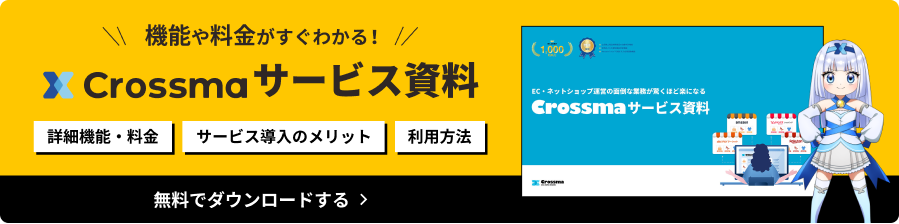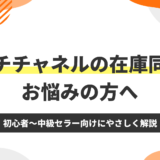商品ページを一生懸命作って、やっと売上が立つようになったのはいいけれど…
毎日の受注処理や出荷作業に追われて、本来やりたいマーケティングや商品開発に時間が取れない。
実は今の時代、受注から出荷までほぼ完全に自動化できるってご存知ですか?
目次
なぜ今、受注・出荷自動化が必要なのか
通販業務って、商品ページを作った後が本当の勝負ですよね。
注文が入るたびに受注確認、在庫チェック、出荷指示…
これを手作業でやってたら、いくら時間があっても足りません。
特に複数のモールに出店している場合、それぞれの管理画面をチェックして回るだけで半日が終わってしまうなんてことも。
でも実は、この作業のほとんどは自動化可能なんです。
受注自動化の本当の意味を理解しよう
「受注自動化」と聞くと、「注文を自動で受ける仕組み」だと思う方がいるかもしれませんが、それは違います。
ECサイトで注文を受けるのは当たり前の機能ですからね。
本当の受注自動化とは、注文が入った後のデータ処理を自動化することです。
具体的には、こんな作業が自動化できます。
基本レベルの受注自動化
複数のECモールから入った注文を一箇所に集約して、受注確認メールを自動送信。
在庫の自動引当まで済ませてくれるレベルです。
これだけでも相当楽になります。
高度な受注自動化
住所の間違いを自動でチェック・修正してくれたり、決済状況に応じて自動で処理を振り分けたり。
さらには「○○円以上で送料無料」みたいな条件判定や、同梱物の自動判定までやってくれるシステムもあります。
出荷自動化は3段階で考えよう
出荷自動化って一言で言っても、実は段階があるんです。
どこまで自動化したいかで選ぶシステムも変わってきます。
第1段階:データ処理の自動化
受注データから出荷指示書を自動作成し、配送方法も自動で振り分け。
送り状番号の取得から顧客への通知まで、データ上の処理はすべて自動でやってくれます。
第2段階:物理的作業の自動化
これが本格的な自動化。
商品を集めて、自動で梱包・検品。
配送ラベルの貼付まで機械がやってくれる世界です。
最新の自動化倉庫では、ロボットアームが的確に商品をピッキングし、搬送ロボットが効率的に商品を運んでいます。
第3段階:外注先との完全連携
3PL倉庫など外部倉庫への出荷指示から、出荷完了の実績データ取得、追跡番号の顧客連携まで、すべて自動で回る仕組みです。
もはや人の手を介さずに注文から発送まで完結してしまいます。
実際に使えるシステムを比較してみよう
理論はわかったけど、実際どのシステムを選べばいいの?という話ですよね。
主要なシステムの特徴をまとめてみました。
導入しやすさ重視なら「ネクストエンジン」
月額3,000円からスタートできて、30,000以上の導入実績があるから安心感は抜群。
アプリが豊富で、必要な機能を後から追加できるのが魅力です。
とにかく自動化率を上げたいなら「クロスマ」
特許取得の出品機能がウリのクロスマですが、受注処理は完全自動なうえに倉庫連携も自動。
出荷までをトータルで90%以上効率化できます。
出荷に特化するなら「シッピーノ」
出荷業務の自動化に特化したシステム。
物流会社との連携が豊富で、冷蔵品や医薬品など特殊な商品の自動出荷にも対応してます。
本格的にやるなら「LOGILESS」
OMS(受注管理)とWMS(倉庫管理)が一体型になった高機能システム。
月額2万円からと少し高めですが、その分できることも多いです。
自動化すべきところと手動を両立できる「GoQSystem」
注文データの自動振り分けはもちろん、各種外部倉庫、フルフィルメントサービスとも自動連携しているOMS。
納得行くまで電話サポートしてくれるから、導入時の挫折は皆無。
実際のところ、費用対効果はどうなの?
自動化システムって導入費用が気になりますよね。
でも実際に計算してみると、意外と早く回収できるんです。
中規模事業者(月間500件程度)の場合、年間で約180万円の人件費削減効果があるのに対し、システム費用は年間36万円程度。
ROIは400%という結果になりました。
さらに、段階的に自動化を進めることで効果を実感しながら投資できるのもポイント。
最初は受注処理だけ自動化して30%の工数削減、徐々に範囲を広げて最終的に95%の自動化を目指すという進め方が現実的です。
自動化導入の現実的なステップ
いきなり完全自動化を目指すのは無謀ですよね。
段階的に進めることで、スタッフの慣れとシステムの安定化を両立させましょう。
まずは現在の業務フローを詳細に分析することから始めます。
どの作業にどれくらい時間がかかっているのか、どこでミスが起きやすいのかを把握することが重要です。
次に、最も効果が出やすい受注処理の自動化から着手。
複数モールの受注を一元管理できるだけでも、相当な時間短縮になります。
システムが安定したら出荷処理の自動化、最終的に物流連携まで含めた完全自動化を目指すという流れが王道ですね。
自動化の落とし穴と注意点
夢のような自動化ですが、100%完璧ではありません。
現実的には95%程度の自動化が限界で、イレギュラーな注文や特殊な要求には人的対応が必要です。
また、システム間の連携が不安定だと、かえって手間が増えることも。
導入初期は手動処理との併用期間を設けて、段階的に移行することが成功の秘訣です。
スタッフの教育も重要なポイント。
自動化が進んでも、システムの監視やイレギュラー対応はやはり人がやる必要がありますからね。
まとめ:今こそ自動化で業務革新を
受注から出荷までの自動化は、もはや「できたらいいな」レベルの話ではありません。
競合他社との差をつけるために必要不可欠な投資になってきています。
月額数千円から始められるシステムもあるので、まずは小さく始めて効果を実感してみることをおすすめします。
浮いた時間でマーケティングや商品開発に集中できれば、売上アップにもつながるはずです。
商品ページを作った後の面倒な作業から解放されて、本当にやりたいことに集中できる。
それが自動化の最大のメリットなんです。