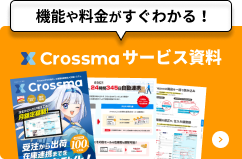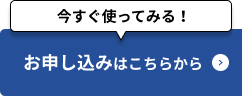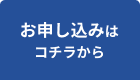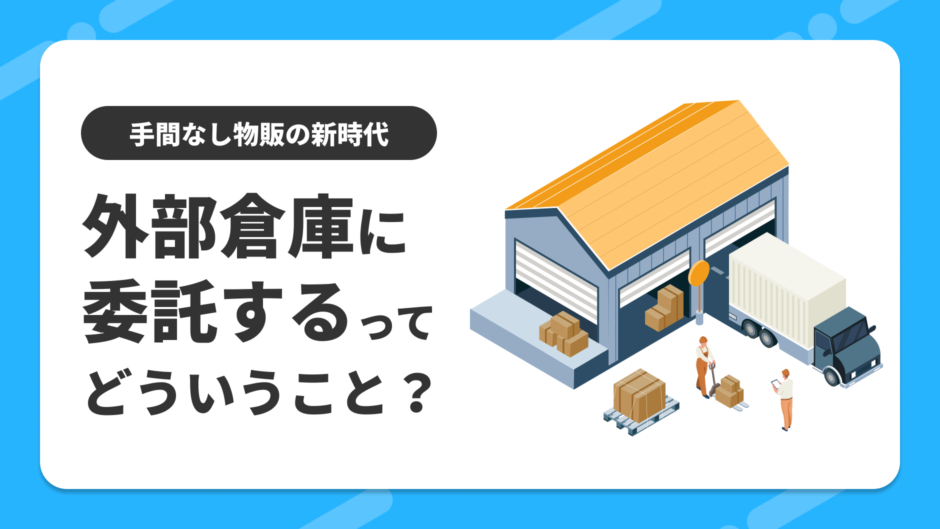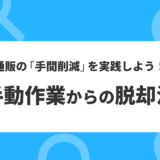ネットショップ運営をしていると、
「出荷作業に人件費がかかってしまう」
「在庫管理が面倒」
「売れるほど困ってしまうから、実際よりも少ない在庫数にして出品している」
と困ったことはありませんか?
商品が購入されたはいいものの、その後のピッキング、検品、梱包、納品書封入、発送というところにはどうしてもマンパワーが必要。
売れれば売れるほど忙しくなってしまうため、物量を調整するショップさんも少なくありません。
売上をアップさせたいのに、上限を決めてしまうのはもったいないですよね・・・
今回は、限られた人手で、「人件費もできるだけ削減したい」という方向けに、「外部倉庫連携」について解説していきます。
目次
こんなご要望がある方にオススメ
売れてほしいのに売れると困る
毎日の梱包・発送作業に時間を取られ、本当にやりたい商品開発や仕入れに集中できない、というお声が増えてきました。
特に月間の出荷件数が200件を超えるあたりから、自社での発送はかなり大変。
1日あたり10件の出荷でも、
- 箱を組み立てて
- 検品して
- 梱包して
- 送り状ラベルを貼って
- 納品書を入れて
- 追跡番号をモールに入力して
- メールを送る
というルーチンが発生します。
出品から出荷まで自動化したい
複数モールに出店していると、
- それぞれのモールで受注を確認して、メールを送付
- 本日出荷予定の商品数、送付先情報をデータ化して
- ピッキングを行い
- 検品・梱包・ラベル印刷
- 送り状番号を入力してメール送付
といった作業が発生します。
これらの作業は出店先の数だけ増えますので、人手が足りない状況に輪をかけます。
一元管理システムの導入でこの状況はかなり改善できますが、とりわけクロスマを使えば「出品したらあとは放置」「寝ていても完全自動出荷」が実現できると嬉しいお声をいただいています。
とはいえ、出荷数が増えれば増えるほど、マンパワーが必要な「出荷作業」については、一元管理システムを導入したとしても上限があります。
外部倉庫連携とは
外部倉庫連携というのは、ネットショップでの受注データを外部倉庫に送り、外部倉庫側で発送してもらう連携のことです。
通常はCSVでの連携になりますが、各社OMSおよびWMSのAPI機能を使うことにより、「寝てても商品が発送される」状態を作ることができます。
主要な外部倉庫サービスは、皆さんも知っている下記の通り。
Amazon FBA
Amazonの倉庫ネットワークを使ったサービス。
基本的にはAmazon上で販売をしている事業者向けですが、楽天市場やauPayなどで売れた注文データをFBA倉庫に発送依頼することもあります。
楽天RSL
楽天スーパーロジスティクス。
楽天と日本郵便の倉庫ネットワークです。
こちらも楽天販売分を自動発送できるだけでなく、Yahoo受注分を発送依頼することもできます。
その他の外部倉庫
上記のようなモールオフィシャルの外部倉庫とは別に、各ネットショップの配送をまとめて受託している物流倉庫があります。
複数のネットショップの商品発送を請け負っていて、ラッピングの数が多い・発送が早い・食品に強い、など各社メリットが異なります。
しかし外部倉庫自体は各社ごとにAPIを持っているわけではないため、受注データの連携はCSVを用いるか、倉庫側が使っているWMS(WarehouseManagementSystem:倉庫管理システム)に合わせる必要があります。
各商品を誰でも把握。商品の状況を正確に管理できるWMS
倉庫内にある商品や資材の入出庫や在庫管理を効率化するためのシステムです。
WMSを導入していない場合のヒューマンエラー
紙の台帳やExcel管理では、在庫数のズレや人的ミスがどうしても出やすいものです。
とくに自社出荷を行っている事業者では、在庫数の管理が目視・紙ベースになりがち。
- 「似た色・似たサイズの、間違えた商品を出荷してしまった」
- 「在庫数の記入ミスで、商品が足りなくなってしまった」
- 「慣れていない人が、重複出荷した」
といった問題がよくあるヒューマンエラー。
WMSを導入するメリット
WMSを使うことで、入荷・出荷・棚卸・ピッキング(商品を取りに行く作業)まで、全部システムで一元管理できます。
- 誤出荷が減る
- ハンディ導入で在庫数管理が正確になる
- 慣れていない人でも、ハンディ導入でミスなく出荷
などといった点がメリット。
最近ではAIやセンサーとも連携できるWMSも増えていて、在庫状況をリアルタイムで把握したり、作業ミスを自動で検知したりできます。
主な機能としては、入荷管理・出荷管理・在庫管理・棚卸管理・ピッキング最適化など。
導入すると「どの商品がどこにいくつあるか」「次に出荷するべき順番は?」のような運用が誰でもすぐ分かるようになるので、人手不足や教育コストの悩みが減り、正確性と作業スピードもアップします。
さらにクラウド型であることがほとんどで、パソコンが苦手でも、どの商材でも導入しやすいようになっています。