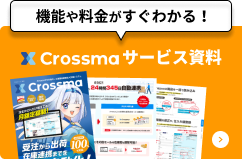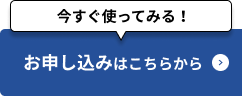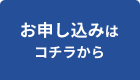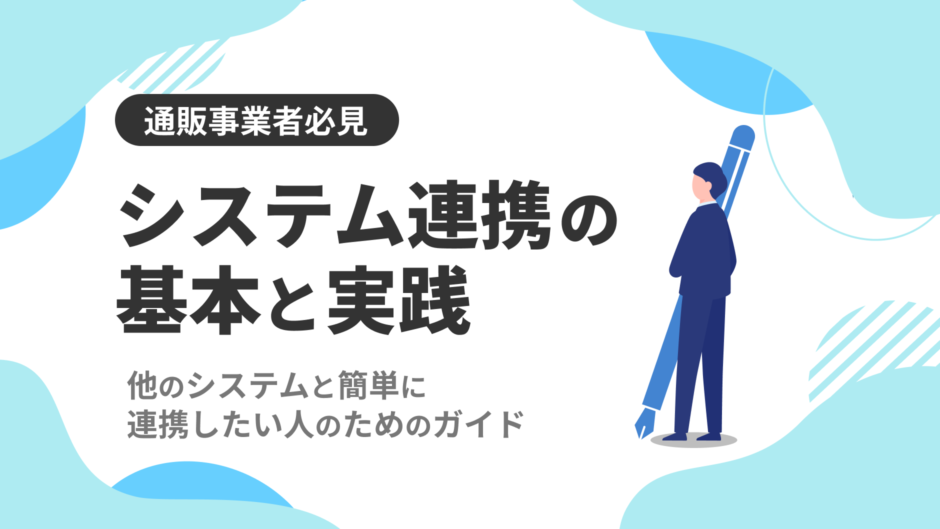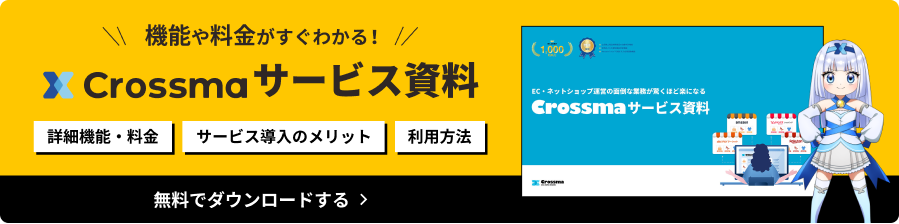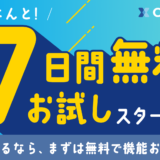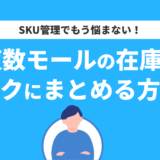ネットショップを運営していると、どんどんエクセルが増えてしまいませんか?
注文データ、在庫数、配送情報、会計数字。。。
日々取り扱うデータが雪だるま式に増えていきます。
「そろそろ手作業では限界かも…」と感じたら、次の一手はシステム連携です。
その中心的な仕組みが API 連携。
この記事では「システム連携ってそもそも何?」「API って英語で何の略?」「結局どう違うの?」というモヤモヤを、具体的な EC 業務の流れを交えてスッキリ解消します。
目次
1. そもそもシステム連携って何?
システム連携とは、別々に動くソフトやサービスを“つなげて”データを自動で行き来させる仕組みです。
たとえば楽天で入った注文を在庫管理システムへ即時反映し、他モールの在庫数を自動調整。
さらに会計ソフトへも売上をポンと送る。こうした一連の流れが「連携」です。
人手を介さずデータが動くので、入力漏れや転記ミスをグッと減らせるのと、さらに大幅な時短になります。
先輩店舗が「システム連携しないと~」「連携システムが~」と発言していたのを耳にした経験があると思いますが、手間もミスも減らせるのがこのシステム連携なんです。
2. API 連携はシステム連携の必殺技
数年前までの「システム連携」は、各ECサイトからのメールを転送したり、CSVを読み込んだりする人手を介しての連携でした。
「半手動連携」ですね。
しかし今はAPI自動連携が主流。
API は “Application Programming Interface” の頭文字。要は**「システム同士の会話の窓口」**です。
「API連携対応」していると、全自動というわけです。
イメージとしては、
- 在庫管理システムが「ねえ、今の在庫数を教えて」とECサイトに API で問いかける
- ECサイトが「在庫は128コだよ」と API を通じて返事をする
これを24時間・秒単位で完全自動で繰り返してくれるのがAPI連携。
CSVをダウンロードしてシステムに読み込んだり、受注内容メールを転送したりするような昔ながらの方法と違い、リアルタイムかつ完全自動で情報が噛み合います。
3. 「システム連携」と「API 連携」はどう違う?
- システム連携 … データをやり取りする仕組み全般
- API連携 … その中で最もポピュラーかつ高速な接続方法
つまり「犬」と「柴犬」の関係に近いイメージ。
APIは、システム連携ファミリーの中にいるスター選手です。
比較して優劣をつけるものではなく、「連携手段の一つ」として捉えましょう。
4. 現場で役立つ「システム連携」のイメージ
4-1 受注データ×在庫管理
複数モールの注文を一か所で受け取り、在庫数を自動マイナス。
売り越しを防ぎ、欠品クレームを削減します。
ここでは、
- どこのサイトで
- 受注日時はいつで
- 何が(商品名と商品コード、バリエーション)
- 何個売れて
- 他モールに同期した在庫数はいくつ
といったデータをやり取りしています。
4-2 WM(倉庫管理システム)とのリアルタイム連携
注文が入った瞬間、倉庫側でピッキングリストが生成されるので、スタッフは紙の伝票を探す手間ゼロ。
午前中の注文を当日発送しやすくなります。
- 受注日時
- 注文者の名前、電話番号など
- 何を、いくつ買ったか
- 梱包時の注意事項
- お届け先の名前、住所、電話番号など
- お届け日時
を、各モールから自動で読み込み。
さらにWMS倉庫で出荷が完了すると、
- ピッキング完了日時
- 送り状ラベルの荷物追跡番号
- 出荷完了日時
を、取得元モールの各受注に自動で反映します。
4-3 会計ソフトへの自動仕訳
売上・送料・手数料をAPIで即仕訳。
決算前に慌てて入力する必要がなくなり、経理コストを圧縮できます。
- 売れた商品
- 売れた個数
- 売れた日時
- それぞれの注文に対しての、梱包資材、送料、モールへの手数料
などを自動で連携しておけば、エクセルも減るしミスも計算時間も短縮できます。
4-4 CRM/MA への顧客データ連携
「2 回目購入」「高単価商品購入」などの条件をトリガーに、リピート施策メルマガを自動配信。
人手でわざわざ目視で抽出しなくても、効率的にアプローチし、機会損失ゼロへ。
5. システム導入で失敗しない4つのコツ
目的を紙に書き出す
このコラムを見てくださっている人は、なにかしら「◯◯をしたい」という目標があるのではないでしょうか?
- 発送遅延を減らしたい
- 入金確認を自動化したい
- 梱包発送までの手間をカットしたい
- 在庫切れになるリスクを抑えたい
- 在庫同期を自動化したい
- 全サイトで共通の在庫数にしたい
このような目標、希望・要望があると思います。
まずは「発送遅れをなくす」「在庫差異を 0.5%以内にする」などゴールを数字で決めると判断軸がブレません。
通販効率化、ネットショップ支援のツールはたくさんあるのですが、それぞれのツールに強みがたくさんあり、また強みがにているツールもたくさん存在しています。
「システム連携」「自動化」を考えているなら、一番叶えたいのは何か、という点を意識しながら、他の機能や価格を比較していく必要があるからです。
APIの有無と仕様をチェック
連携したいサービス同士がAPI連携できるかを確認しましょう。
いまはほとんどのモール・カート、効率化システムがAPI対応しています。
しかしながら、APIでの連携ができないシステムも存在しています。
完全自動を希望するならAPI連携ですが、任意のタイミングで任意の項目のみ連携したい場合は、CSV連携などほかの連携でも結果が得られる場合があります。
上記のとおり目的を設定し比較検討しながら、各サービスの担当者に相談しましょう。
まとめ:効率化できた会社が利益を伸ばせる
注文が増えるほど、手作業はボトルネックになります。
「売上が増えたら考えるか~」という方もいらっしゃるかと思いますが、今ある手作業を自動化するだけで、販促企画の時間が増えます。
システム連携、とりわけ API 連携をうまく活用すれば、
- スタッフは入力作業から解放
- ミスやクレームは激減
- レスポンスが速くなり顧客満足度アップ
「今の業務フロー、どこが詰まっている?」と感じたら、まずは手描きの業務フロー図を作ってみてください。
可視化すれば、どこを効率化すべきか一目瞭然。
つながる力が、あなたのショップを次の成長ステージへ連れていきます。